はじめての中国・アジア転職コラム
海外就職ノウハウ 2024-11-18
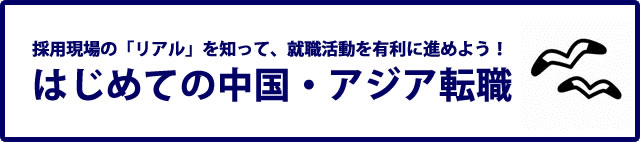

中国では土日に振替出勤日がある!
中国の祝日は7つあり、それぞれ、元旦(1日)、春節(3日)、清明節(1日)、労働節(1日)、端午節(1日)、中秋節(1日)、国慶節(3日)と呼ばれています。中国の連休でひとつ注意すべきなのが、振替出勤日があることです。7つの祝日に前後にある土日を繋げて、3連休や大型連休が作られるため、祝日につなげた土日の分を振替出勤しなければいけません。 |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
 |  |
爆竹を鳴らしたり、月餅やちまきを食べる独自の風習
中国の祝日の由来についてもそれぞれチェックしてみましょう。
華北エリア
華南エリア
その他のエリア
営業・企画・マーケティング
(212)事務・総務・経理・財務・秘書
(41)仕入れ・購買・物流・貿易
(43)生産管理・品質管理・工場長
(81)コンサルティング、金融・財務会計
(21)事務系専門職(会計士・弁護士、士業)
(6)技術系専門職(製造業エンジニア、開発・研究)
(153)IT・通信・WEBサービス
(38)建築・土木・設備・施工・不動産・インテリア
(34)コールセンター・顧客サポート
(9)旅行・サービス関連職
(13)飲食・フード・小売り・販売
(20)広告・クリエイティブ
(31)通訳・翻訳
(9)日本語教師
(10)マネージャー・管理職
(26)経営・事業企画・経営層
(8)その他(美容・医療関連・教師・保育園、団体・官公庁)
(54)
<求職者の皆様にお願い>
カモメに掲載されている求人情報は、求人掲載企業に対して求人情報に虚偽がないようにお願いはしておりますが、掲載内容の全てを保証するものではありません。労働条件・待遇等については、ご自身で企業に十分確認されることをお願い申し上げます。また、求人掲載内容と実際の労働条件が著しく異なる場合、大変お手数ですが以下までお知らせいただけますようお願いいたします。弊社から求人掲載企業に誤記・虚偽がないか確認をさせていただきます。ご連絡先:info@kamome.cn