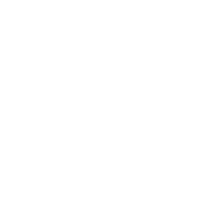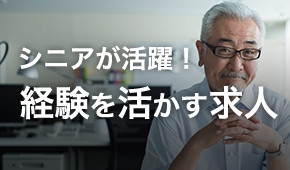その他
【彼女たちの上海】vol.5 菅野真子さん
海外就職体験談 2011-07-01
|
中国へ来たのは衝動に駆られて。この1年半の中国経験ですこしずつ進みたい方向がはっきりしてきた気がするんです。

| 菅野真子さん 東京都出身 |
今、上海で働いている日本人女性がすべて、
仕事やキャリアアップが目的で来ているわけではない。
ある人は好きな人を追いかけて、ある人は日本での生活に疲れて、またある人は中国への興味のため。そういう人も実は少なくない。彼女らは『結果として中国で働いている』だけなのだ。一部には『生活がしたいというだけで中国にいること』に対して冷ややかな目で見る人もいる。『キャリアアップ』とは、そういう世間の冷たい目に対する隠れ蓑として重宝されている言葉なのかもしれない。さて今回紹介する菅野さんも仕事やキャリアアップ目的で中国に渡航したわけではない。彼女の目的はハンセン病回復者が住む村をサポートするボランティア活動である。
ハンセン病回復村ワークキャンプとの出会いから。

中国へのきっかけは国際基督教大学時の交換留学。その留学先が中国になったのも「たまたま」であって、菅野さんはいわゆる中国好きというわけではなかったと言う。
「今から4年前になるんですが、その当時の北京は不便もなくて、中国での文化の違いに苦しむこともありませんでした。留学先の学校では、アメリカ人が中国語を学ぶプログラムに一人で入ってしまったので授業は英語だったりもして、中国にいるのに中国にいるような気がしなかったんですよね。北京にいても自分がシャボン玉の中にいるように、外の世界が別次元のように思えたんです。留学の終わりが近づいた時、ここに残りたいというよりも、ただただ消化不良という気持ちが強くて」
もっとリアルな中国に触れてみたいと、アルバイトなどを探した。その時インターネットで見つけたのが中国でハンセン病回復者の住む村でワークキャンプをするNGOを設立した日本人が発信しているサイト(※1)。サイトを見た時、言葉で言い表せない何かを感じた。
「もともとの目的とはまったく関係なかったんですが、その人の想いを読んでいたらこの人に会ってみたいと思ったんです。すぐに連絡して広州のサポート団体の代表の家へ向かいました」
菅野さんは、子どもの頃、老人ホームに慰問に行っていたという。喜んでもらうことがうれしかったそうだ。ただその頃は「ボランティアをする」という気持ちでやったこと。しかし広州での経験は「自分や仲間がやっていたことが、それは“結果的にボランティアと呼ばれているもの”だった」といい、それは「与える側、与えられる側」といった一方通行の関係ではなく、村に住む彼らから多くのことをもらっているし、学んでいるからだという。
「ハンセン病回復村は中国に600数箇所あり、人里離れたところで暮らしています。私がはじめて参加したワークキャンプでは水道やトイレがないような場所を改善するような重労働から、ただ村の人たちとふれあうことまでいろいろ。村の人たちといろんな話をすると、厚みというか魅力を感じて、今まで会った誰よりもずっとすごいと私は思っているんです。活動自体も同年代が中心ということもあり、楽しかった。いつも笑っていて仲が良かったんです」
ボランティア団体の代表の家に住み込み、そこに同じ目的でやってきた中国の大学生たちや、日本から来たハンセン病回復者、日本人キャンパーと一緒に暮らしながら、今までの学生生活では得られなかったものもがそこにはあった。
「今まで出会ってきた人たちは、中国人も外国人もカッコよくいたいっていう雰囲気が強かったんです。外面ばかり気にするというか。広州で会った人たちはとても気持ちがよかった。居心地がよくて、一緒に飲んで、バカやって……もしかしたら仲間ってこういう感じなのかな、その生活の中で思ったんです」
日本の会社へ入社して一年。
大切な人の死がきっかけで、中国へふたたび。

約2ヶ月の広州滞在後、日本に帰国。大学を卒業し、コンサルティング会社に就職。ボランティア活動を通じてお金の重要性を知ったこともあり、お金を持っている人の考え方や、稼ぎ方を知りたいと思い、経営者を相手に商売するコンサルティング会社へ入社する。
「ボランティアは楽しかったんですが、運営の難しさも痛感しました。学生主体の団体なので、お金も経験も知識もない。組織にとって大切な人が辞めていくのを止められない。だから社会に出るなら、お金をちゃんと稼げるようになりたい。組織を動かせるようになりたい。ちゃんと何かできるようにならないとと思ったんです」
入社してすぐのころに、「志を持つ」というテーマで1時間もらって発表する機会があったそうだ。中国でのボランティアの話をしたところ、会社が村に井戸を作るお金を出すことを提案。さらに会社の寄付で完成した井戸を見に、会社の上司や社員数人を連れてその村に訪問することになったそうだ。
社会人生活が一年を過ぎようとしていた頃、大きな決断をする。菅野さんがワークキャンプでよく訪れていた村で生活していた彼女にとって大切な人が亡くなった。
「村に住んでいる人たちはみな50代以上。ハンセン病はもう回復しているものの、村の生活環境は都市のように整っておらず、病院に行くお金がないこともある。そのため体力が衰えて、日本では治るような病気で亡くなっていくんです。私が活動に参加してからも、村の人がどんどん亡くなっていく……それを見ていると、私が一人行っただけではどうにもならないと頭では分かっているのですが、どうしても現地で生活してみたいと思ったんです。」
実は仕事にも若干の行き詰まりを感じていたこともあって、ボランティア活動への支援に理解のあった会社には感謝と多少の引け目を感じながらも、自分の直感に従って中国に再度来ることを決意する。
本当に役に立てる存在になるために。

“最初に内定がでた会社”という理由だけで、上海勤務の仕事に転職。上海に来てからは、長期の休暇が取れる時には湖南省など遠方の村へ、週末には上海から“近場”にあるハンセン病回復村へ片道5時間かけて通う。しかしこの2011年1月、せっかく中国に来たもののまたもや逆戻り。“日本勤務”の辞令を言い渡される。実は上海での仕事ぶりが評価されて、日本マーケットの開拓要員として白羽の矢が立てられたのだ。
「転勤を聞いた時はショックでした。ただ、こちらに来て、とりあえず自分の気が済むまでやってみて。その中で今の自分の活動のやり方にも限界を感じていました。何をすればもっと村の人の役に立てるか、日本に帰ってみて考えるいい機会だと思っています。」
日本への異動前、昨年のクリスマスに湖南省の村へ行ったそうだ。現地への旅費、宿泊費、村の人たちへのプレゼントとして持っていった粉ミルクも当然ながら自腹。これがその場しのぎでしかないことも、菅野さんは当然わかっている。
「また中国に戻ってくるのかと聞かれると、正直今はNOです。今ここにいるのは、たまたま中国でハンセン病回復者の彼らに出会ったからということだったと思うんです。ボランティアやNPO活動の最先端といわれる地域にいって、そこからその場しのぎでない、継続的で組織的な運営方法を学んでみたいと思っています。それが、将来この回復村の活動に還元できるかなとも考えています。」
ハンセン病との出会いから約3年。菅野さんの頭の奥で片時も離れないことがある。
「山奥の奥にある、こんなところに人が住んでいるのかっていうところに鍋をかついで行ったことがあるんです。村はすり鉢状になっていて、その底にまだ若い頃に移り住んだというおじいちゃんが住んでいて。もうそれから何十年も経過しているのに、誰も会いに来たことがない。テレビもラジオもなく日本も知らない。でも会いに行ったらすごく喜んでくれた。一番ほしいものは?と尋ねると、最初は『政府に支払った10元を返してほしい』と言っていたんですが、その他は?って聞いてみたら『もう死にたいなぁ』と。その時の彼の目が今も忘れられません。雨の後、すり鉢の底だから、もうドロドロになった家の中で、1つだけキラキラしたものがありました。それが棺桶。役人がもうすぐ死ぬからここに入りなさいと届けにきたそうです。それを机にその人は毎日ごはんを食べている。日本でも友達で死にたいとか言う人がいて腹立たしい気がしていたんですが、その村のおじいちゃんにはダメだなんて言えない。ハンセン病はずっと誤解されてきましたが、今では理解も進んできているし、中には結婚して、孫もいて、すごく明るい人もいます。でもこの差は一体何なんだろうと」
菅野さんはこの1月から会社から言い渡されたミッション遂行のため、本人いわく“中国より怖い大阪”に生活の拠点を移す。大阪拠点は同僚中国人と二人だけのスタート。事務所は電話も繋がっていないところから始まる。自ら稼ぎ、組織をつくっていかなければならない。仕事とボランティア。実は継続的な組織運営をいかにするかという点においてはそれぞれ変わらない。勢いだけで向かった中国だったが、自分一人が頑張ってもできることは限られていることに気付かされた。組織で何ができるか、どのようにして組織を運営していくのか。今回のミッションである、ゼロから組織を作り上げていく中で、実は今後のボランティア活動に生かせる経験を数多く学ぶのではないだろうか。菅野さんがハンセン病回復村に直接足を運ぶことは少なくなるが、もっと有効な形で村を支援できる、そんな方法を日本のこれから始まる生活の中で、探していくのだろう。
(取材・文/浅香来)
※1 文中の菅野さんが見つけたサイト
■猪突盲進
原田燎太郎さんのブログ
URL:http://blog.canpan.info/tynoon/
■FIWC-CHINA+plus家(JIA)-中国ハンセン病快復村支援プロジェクト
原田さんが設立したNGO団体のサイト
URL:http://fiwc-c.com/JIA/JIA1st.html
【JIA(Joy in Action)とは】
JIAとは中国国内で活動する民間NGOである。JIAは中国語で「家」の発音記号jiaから名付けられている。ハンセン村でのワークキャンプに関わるすべての人々―村人・ボランティアの学生たち・準備に関わるNGOのメンバー・周辺の住民―みんな作業と生活の共有を通して「家族」となるをモットーにまた、FIWCの「言葉より行動を」の精神を受け継いだ形でのJoy In Actionの頭文字をとったものである。(ウェブサイトより抜粋)